議会報告SERVICE&PRODUCTS
議事録&映像
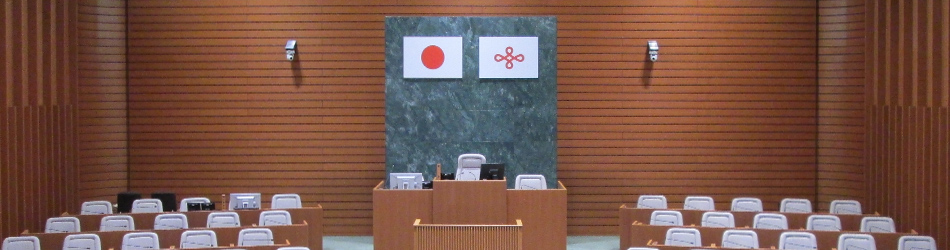
中村なおゆきの本会議場における映像はこちら
令和7年3月定例会 2月26日一般質問
市道細池須脇6号線開通を活かした福地地区の展望は
Q,にしお特別支援学校前の信号・横断歩道・歩道整備は十分か。
A,信号設置については、市道斉藤市子6号線の全線開通後に検討する。横断歩道及び歩道は、現時点では十分と考えている。
Q,西尾市憩の農園・バラ園を地域のシンボルとして整備し、観光振興を進める施策を検討しないか。
A,現時点で、市が主体となってバラ園を再整備する予定はないが、憩の農園ファーマーズマーケットなどは観光拠点となっており、市も西尾産のPRや地産地消推進の場として憩の農園と連携していく。
コンテナハウスを活用した柔軟なまちづくりを
Q,コンテナハウスを活用したまちづくりについて、市の考えはどうか。
A,平常時と災害時に効果的に活用できるため、まちづくりにおいての将来的な可能性はあると考える。
Q,西尾駅東広場や名鉄西尾線の各駅周辺で、コンテナハウスを活用した商業施設やカフェ、コワーキングスペースを整備しないか。
A,地域活性化の可能性があり、中小企業支援の観点から先進事例を調査する。
Q,災害時の備蓄品保管や避難所として、コンテナハウスの活用について市の見解は。
A,コンテナハウスは安全性が高く、避難スペースや応急医療、仮設住宅としての活用を検討していく。なお、災害時には、民間企業との災害協定に基づき、必要に応じて提供を受けることができる。
Q,コンテナハウスを活用して移住希望者向けの「お試し移住住宅」を整備しないか。
A,まずは移住希望者のニーズを把握し、一定の需要があれば、来年度策定する総合戦略で検討していく。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■令和6年12月定例会 12月3日 一般質問
西尾市民病院にふさわしい経営形態は
Q,市民病院が現在抱えている経営上の課題はどのようか。
A,令和5年度決算で約7億円の純損失を計上し、25年連続の赤字となった。医業収益改善のため、不足診療科の常勤医師確保に注力した結果、来年度は医師増員が見込まれている。
Q,患者一人当たりの収益向上に向け、特定診療科やサービスの強化策は検討しているか。
A,手術支援ロボットやレーザー内視鏡治療を導入し、泌尿器科でがん治療体制の整備を検討する。
Q,病院の改革の適切なタイミングや最適な経営形態についてどう考えているか。
A,「西尾市民病院経営強化プラン」に基づき、独自の経営強化策を最優先にして進めており、経営形態の改革は検討していない。医療事情を見極めつつ慎重に判断していく。
重層的支援体制への移行準備の状況は
Q,重曹的支援体制の進捗状況と今後のスケジュールは。
A,本年4月、福祉課に7人のプロジェクトチームを編成し、9月に「コアプラン」を策定した。移行予定を令和8年度とし、事業名を「〜すべての人のために〜つながりの輪支えあい事業」に変更し、移行準備として令和7年度は、庁内連携や多機関協議のモデル支援、地域社会資源や支援メニューの開発を行う。
Q,「断らない相談支援窓口」の設置に向けた準備が進めれているが、どのようか。
A,福祉課の生活困窮担当を核に、官民連携による「断らない相談支援窓口」を令和8年度に開設・運営する計画である。
議事録はこちら
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■令和6年6月定例会 6月5日一般質問
困難事例に対応する基幹型地域包括支援センターを
Q,本市の高齢化率に伴って、介護ニーズはどのように変化していくと見込んでいるか。
A,高齢化率は、26年後の2050年には約8%上昇し、要支援用介護認定者数、介護給付費または介護施設利用者数は現在の約1,3倍に増加すると推計している。
Q,地域包括支援センターは、地域住民からの相談対応に追われ、電話が頻繁にかかっているが、この状況に対して本市はどのような支援を考えているか。
A,ケアマネージャーのスキル向上のため、愛知県市町村振興協会と共催で年2回「介護支援専門員研修」を開催し、多岐に渡る相談支援に対応できるよう支援している。
Q,基幹型地域包括支援センターを設置し、地域包括支援センターの負担を軽減する計画はあるか。
A,基幹型地域包括支援センターの設置計画はない。長寿課を核として、基幹型に求められる役割を担っていると考える。
Q,成年後見制度の効果的なPR方法とは、具体的にどのようなことを考えているか。
A,「いげたネット」を活用し、利用案内や研修情報などを発信することで、必要な方への情報提供に努めていく。
Q,本市における、ひきこもり状態にある方の推定人数と年齢層は。
A,内閣府調査結果に基づき、西尾保健所が算出した推計人数は、15〜39歳では494人、40〜69歳では1142人である。
Q,複合化・複雑化した支援ニーズに対応していく包括的な支援体制を構築しなければ、本市における地域共生社会の実現は困難と考えるがどうか。
A,全世代に対応した総合相談窓口の必要性を感じており、地域共生社会実現のための新たなセーフティーネットとして重層的支援体制整備事業への移行に関する調査・研究に着手した。
議事録はこちら
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■令和6年3月定例会 2月27日一般質問
市街化調整区域の地域活性化を
Q,県が策定した市街化調整区域内地区計画ガイドラインに基づく、本市の対応は。
A,県が策定したガイドラインの基づき、地域の実情に合わせ、これまでに工業系地区計画を11地区、約102ヘクタールで計画決定した。
Q,市街化調整区域における空き家等の現状は。
A,空き家を都市計画区域ごとの分類はしておらず、市街化調整地域での空き家の現状の把握はしていない。市内では4年度末時点で、151件の管理不全空き家があることを把握している。
Q,市街化調整区域内では厳しい建築制限があり、住宅の売買が困難なことから、空き家の増加につながるが、どのように考えているか。
A,厳しい建築制限があるものの、地域コミュニティの衰退を防ぐため、敷地面積が500平方メートル以下の既存住宅については、特定の条件下で売買が許可され、地域コミュニティの活性化を目指す。
Q,遊休農地や耕作放棄地の発生防止と担い手への農地の集積・集約化の促進を図るため、農地マッチング支援事業を検討しませんか。
A,農業新興地域内の農地に関する意向調査に関する意向調査を基に、農地所有者から担い手や新規就農者へのマッチング及び集団的な農地利用の調整を行うことにより、農地の集積・集約化を図っていく。
地域公共交通について
Q,コミュニティーバスの乗りこぼしを速やかに対応する方策は。
A,今度は市内のタクシーを活用して乗りこぼし対応を行う。
Q,2024年4月に条件付きで利用できる「ライドシェア」について、本市の考えはどのようか。
A,地域の交通事業者の意向を確認し、制度の活用可能性について注視していく。
議事録はこちら
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■令和5年12月定例会 12月1日一般質問
西尾コンベンションホールの運営状況は
Q,交付している補助金の主な補助事業内容と事業効果、現在の財政状況、最近の利用状況、稼働率は。
A,補助金は、前年度の賃料の半分と固定資産税の合計額を補助する内容で、令和5年度の金額は約1113万5千円。事業の効果として、講演会や展示会などに利用され西尾駅前の活性化や賑わいの創出に一定の効果が見られる。
令和4年度の財政状況は、減価償却費を除くと約1400万円の利益があるが、補助金を含めると経営は厳しいと考える。利用状況は、会議や新型コロナウイルス感染症ワクチン接種会場などで合計328件であった。稼働率は、大ホールが約40%、多目的ホールが約63%で、新型コロナウイルスの影響を受けて低下したが、現在は利用者が増えている状況である。
不登校・ひきこもりの生徒と障害者の自立を目指して
Q,本市における不登校の児童・生徒数の状況は。
A,令和4年度の不登校の状況は、令和3年度と比べ、小学校が28人増加して183人、中学校が41人増加して373人となっている。
Q,愛知県立にしお特別支援学校の令和4年度の進路状況は。
A,学校への確認では、令和4年度卒業生34人のうち、一般就労が2人、障害福祉サービス利用者として就労移行支援5人、就労継続支援A型が1人、B型が13人、生活介護が11人、その他が2人である。
Q,西尾市基幹相談支援センターが提供するサービス内容は。
A,本市では、障害者相談支援事業を3法人に委託し、令和5年10月からこれらの事業所を基幹相談支援センターとして運営を開始した。このセンターは地域における障害者の相談支援の中核となる機関で、総合的・専門的な相談支援、地域の相談支援事業者への指導や人材育成、様々な機関との連携強化、施設からの地域生活への移行支援などを行う。
議事録はこちら
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■令和5年9月定例会 9月6日一般質問
重層的支援体制整備事業の必要性は
Q,重層的支援体制整備事業の概念とその地域性社会における重要性は。
A,重層的支援体制整備事業は、地域の多様な支援ニーズに対応するための一つの有力な手段とされている。介護や障害、子育て、生活困窮などの分野で、既存の支援体制を活かし、地域住民と関係機関が協力して地域福祉を推進する体制作りが重要と考えている。
Q,本市の現在の支援体制と比較して、重層的支援体制整備事業がもたらす主な改善点はどのようか。
A,既に多機関での協議や横断的なケース検討を行っており、基本的な重層的支援体制が整っている。改善点として、どこに相談したらよいかと迷わせないようなことが必要で、各窓口が広い視野で相談を受け止めるとともに、速やかに関係機関で情報を共有する仕組みが必要である。また、重層事業に移行することで、国の補助金が一体化し、多分野での活動は容易になるというメリットがある。整備の重要な点としては、庁内における合意形成と連結強化、及び調整機能を担う人材育成と考える。
Q,事業の必要性について、市長の理解と認識は。
A,国が推進する重層的支援体制整備が有効であると認識しているが、その組立て方は一様ではなく、市独自の強みを生かしながら、地域に合った包括的な支援体制を模索する方針である。社会福祉協議会と連携し、民間の意見も取り入れていく。
フレイル予防の取組で介護予防の推進を
Q,フレイルの現状、特に高齢者におけるリスクと課題は。
A,フレイルの特徴は、運動機能の低下である。最も注意すべき症状は、転倒や骨折、低栄養や認知機能の低下であり、高齢者に運動機会の提供が重要である。
Q,フレイルチェック事業として「フレイルサポーター」を養成しないか。
A,現状でフレイルチェックの体制はとれているため「フレイルサポーター」の養成は考えていない。
議事録はこちら
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■令和5年6月定例会 6月5日一般質問
西尾市の観光施策は
Q,積極的にバイクツーリズムを推進し、観光産業の成長や地域経済の活性化を図らないか。
A,全国各地から訪れるバイクツーリズムに関するイベントの開催は、観光客の誘客、地域経済の活性化に大いに繋がるものであると考える。本市で、バイクツーリズムのイベントが開催される際は、西尾市観光協会や吉良温泉観光組合等とも協力して支援することを検討したい。
Q,佐久島で、ウエルネスツーリズムやヘルスツーリズムを推進し、島の活性化を図れないか。
A,佐久島は、ヘルスツーリズムには最適な場所である。佐久島にあった「健康プログラム」を考案することは可能であると考えるが、その実施について今後、地元観光の会等に意見を問う。
Q,憩の農園リニューアルにより地域産業への影響はどのようか。
A,オープンして1年が経過したが、年間売上は約20億円で、全国有数の産直施設であり、市内農産物の6次産業化の推進にも大いに貢献している。
暮らしの中で治し・支え・看取る医療を
Q,高齢者の在宅での看取りを促進するための支援プログラムやサービスの充実策を検討しているか。
A,「在宅医療」の体制整備の必要性や「在宅看取り」が大きな問題の一つとして認識している。今後も在宅医療と介護の連携推進に向けた取組を実施していく。
Q,看取りを含めた「人生の最終段階における医療」や「緩和ケアの提供」において、市内の医療機関との連携強化策は検討しているか。
A,医療・福祉・介護・行政など地域の暮らしを支える様々な専門職等をつなげる「いげたネット」というオンラインシステムを導入している。院内に訪問介護ステーションの設置を行って緩和ケアチームなどと連携し、看取りも含めた在宅医療の強化に取り組んでいく。
議事録はこちら
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■令和5年3月定例会 2月28日一般質問
安心して住み続けられるまちづくりを
Q,水道基本料金の無料化について、住民から「継続してほしい」との声を聞くが、長引く物価高騰を踏まえ、どのように考えるか。
A,水道事業単独での基本料金をはじめとした料金の無料化は考えてない。
Q,市内の中小企業や個人事業主に対する本市の支援はどのようか。また今後、新たな新型コロナ・物価高騰対策の支援策を考えてないか。
A,中小企業や個人事業主に対して、令和4年度は「SDGs推進事業者応援補助金」と「カーボンニュートラル推進事業者支援補助金」を実施している。今後の支援策として、事業者との情報交換を行い、国や県の支援制度を情報収集し、効果的な事業を検討していく。
Q,教育費の負担が大きい世帯への支援策として、中学校給食を無償化にしないか。
A,給食費の無償化ではなく、老朽化した学校施設の改善など、安心で快適な教育環境の整備を進めていくことを優先する。
Q,各種支援情報について、市民が理解しやすいよう、市ホームページに支援情報一覧を掲載しないか。
A,市民が必要な情報に早く到達できるよう、今後は、各部局が発信している支援情報を集約した一覧のページを設けるとともに、トップページに物価高騰対策支援に対するバナーを設置する。
「食」に関する取組は
Q,食品ロスを減らす取組として「公共冷蔵庫」を設置しないか。
A,誰でも利用できる冷蔵庫の設置となれば課題が多く、現状では困難である。市内のコンビニエンスストアと提携して食材等の回収BOXの設置を検討している。
Q,ヤングケアラーとその家族を対象に配食サービスを提供し、家事の負担軽減を目指さないか。
A,兵庫県がモデル事業として開始している。どのような支援が適当であるかを検討し、判断していく。
議事録はこちら
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■令和4年12月定例会 12月1日一般質問
佐久島における介護サービスは
Q,佐久島いきいきサービスについて、事業内容や利用状況の詳細はどのようか。
A,事業内容は、主に健康体操、健康チェック、カラオケ、ゲーム、作品作りなどレクリエーションを行っており、週3回佐久島開発総合センターで午後1時から4時まで開催している。利用状況は、現在参加者4名である。
Q,高齢者に関する行政の情報を島内でどのようなネットワークを通じて共有しているか。
A,行政の情報は、広報、回覧板などのほか、地域包括センターの訪問や相談会、また、従来からの地域のつながりを生かして民生委員が細やかに活動されている。島内の高齢者からの情報は、地域包括支援センター、介護事業所などが把握し、地域包括支援センターが開催する情報交換会において関係者間で共有しており、今年度は2回開催する予定である。
Q,高齢者配食サービスについて、佐久島が除外されている状況を直ちに是正すべきと考えるが、どうか。
A,現在のところ配食の利用につながっていないが、直ちに佐久島を対象区域に含めることは難しい。有償を含めたボランティアの活用などを視野に入れながら、地域と一緒に有効な手立てを研究していく。
Q,今後、島内において、在宅医療のニーズが増加すると考えられるが、離島における介護サービスについてどのように考えるか。
A,在宅医療のニーズが高まるものと認識している、離島医療と介護の連携強化が今後の課題である。
Q,サービスの種類と量には地域格差があるが、どのように考えるか。
A、令和6年度から3年間のサービス需要量の見込みを行い、それに対応するサービス提供体制を確保していきたい。
議事録はこちら
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■令和4年9月定例会 9月2日一般質問
農水産業に対する支援や活性化対策は
Q経営者不足問題を抱える畜産農家はどれくらいあるか。
A世帯主が65歳以上で後継者がいない畜産農家、もしくは未定である畜産農家の割合は、全体の2割ほどになる。
Q酪農ヘルパー制度の導入について、どのように考えるか。また、その活用状況と問題はどのようか。
A酪農ヘルパー制度を活用することで、一年を通して計画的な休暇の取得が可能となり、ゆとりある畜産経営ができるものと考える。現在16戸の酪農家に対して、3人のヘルパーが従事しており、1戸当たりのヘルパーの月平均活用日数は、約4日になる。問題点は、飼料高騰等酪農経営が圧迫し、ヘルパーへの支出で、経営がさらに厳しくなる。
Q耕作放棄地の活用の問題について、どのように考えるか。
A耕作放棄地の活用には、耕作を希望する担い手とのマッチングが重要であると考え、農地バンクを活用した利用権の設定を推進している。
Q飼料高騰による畜産農家や化学肥料高騰による農家への影響はどのようか。また行政としての物価高対策はどのようか。
A飼料高騰による畜産農家の経営状況は厳しく、国や県による配合飼料の価格の補てんが行われている。
今後も国や県に対して補助事業等の要望を行い、農業者に有利となる補助事業の確保に努めていく。
Q花きの需要が減少していると思うが、新たな取組をしないか。
A今年度、新たな取組として「西尾の花販路拡大プロモーション」を実施している。
Qかつて福地地区で盛んに生産されていた菜の花を核にした「食・農・観」で地域活性化を目指さないか。
A現在は考えていないが、この地区を中心として一色さかな広場や道の駅にしお岡ノ山、地元農水産物を取り扱う飲食店への来客を図る事業を予定している。
議事録はこちら
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■令和4年6月定例会 2022年6月7日一般質問
障害者雇用の促進を
Q現在の市役所および市内の民間企業における、障害者の法定雇用率はどのようか。
A令和3年6月1日現在で、西尾市役所が2.6%,ハローワーク西尾管内の民間企業が1.84%となっており、民間企業については未達成という状況である。
Q障害者就労支援施設へ仕事を確保し、経営基盤強化のために、「封入・封かん業務」を委託しないか。
A前年度の住民税非課税世帯等臨時特別給付事業において、対象者への通知約9千通の作業を就労支援事業者に委託した。
物品等を調達する際には、障碍者関係事業所の活用を働きかけ、機会拡大の推進に努めていく。
Qにしお特別支援学校を卒業した後の進路について、具体的な支援策をどのように考えているか。
A毎年、卒業予定者の進路希望の情報を提供していただき、必要なアセスメントなどを学校と調整するとともに、相談支援事業所と連携しながら、就労支援などの適切なサービスにつなげていくよう努めている。
新型コロナウイルス感染症対策の現況や予防接種健康被害救済制度は
Q市内における新型コロナウイルス感染者は何人か、また、過去に罹患された住民に対して、アンケート調査を実施しな
いか。
A初発感染者から令和4年5月23日までの間の累計で1万3021人となっている。
感染者の情報は県西尾保健所が保有しており、実態を把握することはできないことから、アンケート調査の実施も困難な
状況である。
Q予防接種を受けたことにより、障害が残ってしまったり、亡くなられたりするなど、健康被害の報告は。
A予防接種健康被害救済制度の案内後、厚生労働省に進達した方は4件。
内訳は多発性脳梗塞の発症が1件、接種した上肢の痺れの継続が1件、死亡が2件である。
議事録はこちら
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■令和4年3月定例会 2022年3月1日一般質問
「地域防災」に対する取組は
Q、家庭での食料品備蓄の普及に向けた取組や市民への周知、情報発信する上での工夫はあるか。
A,家庭での食料品の備蓄の周知については、救援物資が届くまで時間がかかる場合があるため、ハザードマップ、ホームページ、広報などで水や食料品を1週間分備蓄してほしい旨を周知している。
また、防災カレッジ、災害クッキング講座、出前講座など市民に直接伝える機会にて、具体的な備蓄の方法などを周知している。
西尾城址周辺の活性化を
Q,西尾城址に対する景観保護や町並み保存の具体的な考え方はどのようか。
A,「西尾城跡保存活用計画」に基づき、今も残る石垣や土塁などの保存を進め、西尾城が整備された江戸時代前期の景観を体感できるよう、天守台から本丸丑寅櫓の見通しを遮る樹木の剪定や伐採をする。
また、現在は残っていない土塁や櫓、門などを可能な範囲で復元していくことも検討していく。
Q,観光振興や美しい町並みを形成するため、西尾市歴史公園周辺の電線の地中化を図らないか。
A、西尾城二之丸跡北側県道の電線の地中化は、美しい町並み形成に効果があるものと考えている。
県道の電線地中化を進めるには県の協力が不可欠で、今後の二之丸跡地内および周辺の整備の状況を踏まえた上で、関係部局と調整していく。
Q,天守閣の建設および城内整備の計画についての考えはどのようか。
A,天守閣の建設は、今後30年以内の建設を目指し、寄付金で賄う。
議事録はこちら
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■令和3年12月定例会 12月3日一般質問
子育てしやすい環境づくりを
Q,病児・病後保育はどのようか。また現状において課題はないか。
A,エルザの家では、病児・病後児保育を実施しており、利用実績としては、令和元年度が139名、2年度が13名、3年度は50〜70名程度と想定している。中野郷保育園では病後児保育を実施しており、令和元年度が41名、2年度が12名、3年度は39名程度と想定している。中野郷保育園は、本年度中に園舎の建て替えが完了し、令和4年度から新園舎内での受け入れが始まり、施設面での充実が図られる。
Q,日中一時支援サービスの現況はどのようか。また、利用者や事業所からの要望や課題はないか。
A,ここ数年減少傾向にあるのは、新型コロナウイルス感染症の影響で、サービスの利用控えがあったことや、事業者がサービスの提供を一時休止したことなどが考えられる。課題としては、日中一時支援を放課後等デイサービスの補完として利用される場合が多い中で、放課後等デイサービス事業所の定員が飽和状態にある。需要が高まり、支給調整が必要となって希望どおりにできないことや、事業所によって格差が生じないようにサービスの質を維持・向上させていくことである。
障害者福祉サービスの向上を
Q,タクシー料金助成事業について、1枚当たり500円のチケットであるが、利便性向上のため、250円のチケットを発行しないか。
A,現行どおりの運用とする。
Q,視覚障害のある方が、市からの郵便を見過ごさないために、封筒を点字郵便にしないか。
A,視覚障害のある方への情報の伝え方に配慮することは必要なことと考えている。まずは、福祉課から送付する封筒への点字記載について、今後実施を検討していく。
議事録はこちら
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■令和3年9月定例会 9月3日一般質問
コロナ禍における市民安全・安心の確保と経済の活性化を
Q,学校や福祉施設(高齢者施設・障害者施設)等に抗原検査キットを配布して感染拡大を防止しないか。
A,福祉施設のうち入所施設は、職員からの感染を防止するため、症状が現れた場合に検査ができるよう、国が希望施設に対して抗原検査キットを配布している。活用方法については検討していきたい。
Q,空き店舗所有者へ改修費の補助や貸し付けを行い、商業施設として有効活用し、商店街の活性化につなげないか。
A,空き店舗所有者に対しては、市街地の活性化推進を目的として空き店舗の活用に対する補助制度を設けている。
Q,経済対策として、キッチンカーの導入支援事業を展開し、本市の飲食業の活性化を図らないか。
A,キッチンカーの導入支援については考えていないが、キッチンカーの購入費については「がんばる事業者応援補助金」を活用してほしい。
Q,西尾駅の高架下の駐車スペースに商業集積ゾーンとして賑わいを取り戻さないか。
A,名鉄西尾駅周辺の高架下については、現在貸し駐車場として運営会社が利活用しており、これ以外の計画は考えていない。
将来を見据えた福地地区活性化に向けて
Q,西尾市都市計画マスタープランで位置付けられた憩の農園の具体的な内容はどのようか。
A,第1期工事として、地元の野菜や果物、切り花などを販売する「ファーマーズマーケット」の建設を来年春に完了と聞いている。
議事録はこちら
